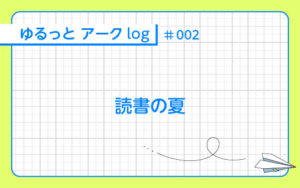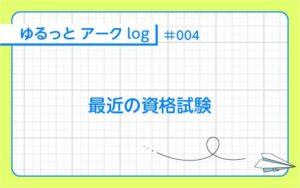美しい組版とは?
こんにちは。本日のブログを担当するKです。
皆さんは、「美しい組版」と聞いて、どんなことを思い浮かべますか?
私がこの業界に入って最初にぶつかった壁。
それが、「美しい組版とは何か?」という問いでした。
そして20年経った今でも、私はその答えを探し続けています。
だからこそ声を大にして言いたい!
日本語組版って、難しくないですかーーーーーーー!?
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号……。
多種多様な文字の組み合わせに加え、縦書き・横書きの両方が存在する。
つまり、それぞれに対応した組版ルールを理解していないと、見た目も読みやすさも崩れてしまうのです。
私が初めて組版作業を任されたとき、頭が真っ白になりました。
フリーズしたのは、機械ではなく私のほうです。
当時は、忙しい先輩の手を借りながら、毎日が試行錯誤の連続でした。
隙を見つけては質問し、必死にメモを取り続ける日々。
でも、どうしてもモヤモヤが晴れない。
「先輩は何を見て、“良い組版”だと判断しているのだろう……?」
終電近くまで作業に追われながらも、この疑問を解消したくて、
自分でセミナーを探しては積極的に参加しました。
印象に残っているのは、初めて参加したセミナー。
登壇者は、海外で活躍する書体デザイナーや、憧れのデザイナーたち。
彼らの仕事の裏話を聞きながら、何かヒントが得られないかと集中していました。
終盤の質疑応答の時間。私は思い切って手を挙げました。
「美しい組版とは、どのようなものですか?」
講師の皆さんは少し考えた後、こう答えてくれました。
「組版ルールはあるけれど、絶対的な正解はないと思う。自分が“心地よい”と感じるところを探している。」
……当時の私は、その答えに少し戸惑いました。
「心地よいって、感覚で判断するの……?」と首をかしげながら、その日は会場を後にしました。
20年経った今、ようやく腑に落ちたこと
今振り返れば、そのときの言葉が、ずっと私の中に残り続けています。
そしてようやく今、実感として理解できるようになりました。
組版ルールは、読みやすさを高め、誤読を防ぎ、全体の統一感を保つためのものです。
でも、日本語組版には明文化しきれない“余白”や“例外”が多く存在します。
たとえば、お客様の要望に合わせた微調整が必要なとき。
ルールではなく、「読み手にとってどうか?」を基準にするしかない場面も多々あります。
そのとき、私が判断の軸にするのが、
「心地よいかどうか」
という感覚です。
視線の流れにストレスがなく、自然と情報が入ってくる組み方。
それこそが、私が思う“美しい組版”の一つの答えです。
「正解がない」からこそ、私は日々この問いと向き合っています。
知識をアップデートし続けながら、今日もまた、新たな“心地よさ”を探しています。
組版という仕事はとっても奥が深いです。